
 |
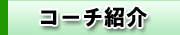 |
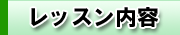 |
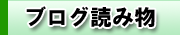 |
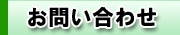 |
|
2018年11月24日更新
「公認審判員研修会」に行ってきました。。。
「3年に一度」更新の必要がある卓球の「公認審判員」資格。 9:30~始まった今日の講師は、日本卓球協会参事の「長谷川敦司」さん! 研修会は講義のみとなり、今回は実技による実践的なことは行われませんでした。 参加者はどのくらいだったかな? 会場いっぱいで150人以上は来られていたかも知れません。 講義の内容を少し書いてみたいと思います。 研修内容は「審判員の手引き」をスポットに当てて行われました。 この「審判員の手引き」とは→「卓球競技の審判法/審判員の手引き」という冊子で、 日本卓球ルールブックを補い、ルールーの解釈のヒントを記しているものを示しているものです。 1. 「最近のルール改定」H30年6月1日改定・実施の日本卓球ルール(改定概要)の別紙より 2. 「審判員の手引きについて」 1)役員・審判長・主審・副審・ストロークカウンター 14)ペナルティー 3. 審判法(前半)についてQ&A … 私たちの身近で関係ありそうな「あるある」を簡単にかいてみました。 ◆「サービス」… 全日本の大会で、「サービスのトスを上げる時、手が台より下がる」例が3割ほどあったそうです。 これは「投げ上げサービス」が増えたことが要因らしいのですが… (練習から気を付けて行きましょうネ) ◆「日本式ペンホルダー」裏面にラバーを貼って使用する場合… 半円のコルク上部からラバーを貼ることができます(その際JTTAなどのマーク部分は残します) また、半円とラバーの間(両サイド二か所)に隙間部分が出来てしまいます。 この部分は(裏面)ラバーの色に合わせましょうとのことでした。 (裏面は)白木ではダメというルールということからです。 これは「初耳」でしたね。 塗っていない場合には、次に出るまでには「塗っておくよう」指導する…とのこと。 また、コルク部分の上からラバーを貼り使用してはいけません(平面性が損なわれる) 板(ブレード)は、硬く・平らなものでなくてはならないからです。 もし貼りたい場合は、コルク部分を平らに削りラバーを貼りましょう。 「グリップ」部分であるので大丈夫という理解でしたが、間違った解釈をしていました。 「シエイクハンド」を使用している方は、あまり気にされない項目ではありますが、 「ペンホルダー」にとっては、グリップ加工などのほか工作作業が必要な時があり、 ルール上どうなんだろうな!と思いながらやっている時もありました。 ◆「ラバーに亀裂…がある」場合… (プレーに支障がない場合)1~1.5㎝ぐらいラバーに亀裂…があってもそのままでといっていました。 それはラケット検査でひっかかってしまうからです。 私は亀裂部分があると、マジックでチョコッと塗っていましたが、ダメなんですね((+_+)) ◆「プレー中ボールが入ってきた」場合… 基本は審判が判断をします。選手は手を挙げるなどしてプレーを続けるのが望ましいです。 (自分の判断でプレーをやめないようにしましょうね) 審判は手を挙げ「ストップ」といってプレーを止めましょう。 ◆「サービスでのフリーハンド」… サーブをするときは、ボールが終始みえるようにしましょう。 サービスは「初めから打ち終わるまでボールが見えていなければなりません」 ・ラケットを持っていない手 ・ボールを投げ上げる手 …をフリーハンドといいます。 テレビなどで放映される大会でもサービス時での「フリーハンド」の引きが遅いように思えます。 このジャッジも審判にて行われますが、左利きの方と対戦するときは、見えずらく「レシーブ」位置をずらして対応することもあります。 また、審判をしていても見えづらい時もありますね。 この項目は、質問として挙げさせて頂き明確な回答はありませんでしたが、講師の先生は「今一度、プレーヤー各々の意識や理解が必要でしょう!」とおっしゃられていましたね。 15:00まで行われました「公認審判研修会」 ボランティア的なことが多いこともあり、審判の更新料など軽減され 多くの方に審判の資格など取りやすさも考えられているようです。 また、学生の方々にも「ルールを正しく理解するためにも」審判の資格へのお考えもあったそうですが、それまでには至らずのようで…。 「研修会」で私たちの出る試合!「そんなことあるなぁ~」を書いてみました。 ここ最近は日本勢の活躍等もあり、テレビでも多くの世界大会の試合が放映され、 トップのプレーを見ることが出来てきましたね(^_-)-☆ スーパープレーなど、スローモーションで見れたり繰り返し映され、 スイングなどわかりやすくなってきました(いいお手本となっています) 逆にサービスなど「あれっ!それでいいの!?」と思ってしまうほどのシーンもあったりして、(おかしな見本?)そんな影響もあるのかな!?なんて勝手に思ったりしちゃっています。 ではでは… |
|