
 |
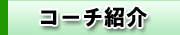 |
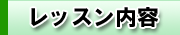 |
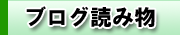 |
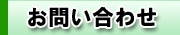 |
|
2016年03月29日更新
卓球やスポーツでは「理論」が必要!!
毎月、スポーツ雑誌が届きます。 興味深い記事が掲載されていました。 私が高校生時代の卓球部では、うさぎ跳びは勿論、連帯責任とやらで体育館の床の上に卓球シューズの侭、長い時間正座させられたり、夏の合宿でうがいは良いが、水を飲んではいけないなんて言われた時代でした。 この摂水の件は、疲れやすいから、根性がないからなどの理由でした。 しかし、今では水分不足の弊害が科学的に実証されたので、このような指導は過去のものと成りました。(^_^)/~ この様に、医学、科学の進歩の事実の判明とともに、スポーツや卓球における理論は、日々刷新されてきました。 卓球世界ナンバーワンの中国では、国技でもあり国をあげて、卓球技術を研究して同じ技術のもと中国選手は練習を重ねています。 日本と中国での違いは、日本の指導者の元の常識や経験則に基づく指導でした。 最近では日本でも、国をあげてJOCアカデミーなどで、日本代表のたまご選手達を育てるように成りました。 最近はスポーツに対する見方が変わって、トレーニングや技術が理論的になってきています。 卓球でも実践的な「ひらめき」から、新しい技術や戦術が生まれています。 例えば「チキータ」や反対回転の「ミュータ」、サーブでは「」王子サーブ」「しゃがみこみサーブ」などですね! その効果や方法を分析・理論化する事で新たなる「理論」と成って実践を支えています。 そして、情報もスピードアップして、今までの常識を変え、皆も経験することが出来るように成りました。 この情報化のスピードアップで、昔の教えは何だったのかな~なんて思われます。 こんな例が掲載されていました。… 1950~60年代では、「女性がマラソンをすると死ぬ」と医者が言っていたが、こっそり練習を重ねていた女性が完走したという。 1960~70年代は、「運動中は水を飲んではいけない」とありましたが、今では反対に「こまめに水分を取りましょう」となっています。 でも、こんな様々な情報も、2年も経てば古くなって、どんどん科学も進んでいます。 ではどうしたら?~ 自分を変えるための「自己観察力」も必要になっています。 「自己観察力」… 体験を積み重ねた理論と そして、疑う姿勢が必要で、科学的トレーニングだけで世界王者にはなれる人はいません。 スポーツには、根性や気合いも重要な要素なんです。 今現在の卓球技術を修正するには「自己観察」が大きな要素で、自分の動きを理解出来れば、次に進めると思います。 それは、自分自身の動きを理解していなければ、フォームや入らない、上手くボールを捉えられないなどを変える事は出来ないからです。 今は、トップ選手達が必ず、ビデオ撮影をしているシーンをテレビで見ます。 私も卓球大会に自分の試合を動画撮影をしていました。 私だけだと思いますが~初めは、観た時に目を伏せてしまう程のシーンが映されていました。 ここで撮影したビデオ映像を客観的・分析的に観察しても、それが出来る様に成るわけではありませんと書かれていました。 「感覚潜入」が必要になるという、映像を観てそこに潜り込んでみる。 自分の頭の中で、その人になり、その人の頭になって自分がやっているイメージを、描いてみる事が必要だということです。 卓球や運動は、偶然成功する段階から、途中またわからなくなり、出来る、出来無いを繰り返します。 この繰り返しをやっていくうちに変わっていく、上手くなっていくと思います。 ①おもしろそう、なじめそうな気がする。 ②分かりそう、分かるような気がする。 ③出来たと感じる、まぐれ、偶然に成功する。 ④何度も成功し、出来るという確信が持てる。 (イ)一応出来るという確信が持てる段階 (ロ)わからなくなる段階 (ハ)もっとよい動き方を身に付ける段階 (ニ)変化する条件下でも出来る段階 ⑤自分が思うままに理論にかなって動ける様になる。 Kクラブ卓球教室の生徒さんからも、全然出来ない時から、段々出来るようになってきた時に、初めて卓球って中々難しいんですね~なんて声が聞こえてきました。 これは、成長している証拠だと思いますヨ(*^^)v…繰り返し繰り返し頑張りましょう☆彡 |
|