
 |
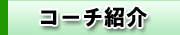 |
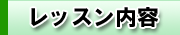 |
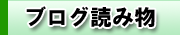 |
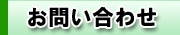 |
|
2014年03月21日更新
湿布‥での温度管理はできていますか?
 湿布などでの温度管理はできていますか? 私は以前、スポーツ時に湿布をしながらしない方が良いと聞きましたが、卓球教室で生徒さん達の湿布姿をよくみかけます。 勿論 私も、卓球試合中や試合後に、筋肉や筋に違和感を感じる時もありました。 そんな時、常にスポーツバックに入れてある、キネシオテーピングや湿布、バンドエイなどでは大いに役にたっています。 でも、常に持っているこの救急用~自分の為に使う時は少ないですが~練習場や試合会場ではみんなの為に役立っている様です。 私は痛みを感じながらの運動時には、湿布ではなくキネシオテーピングやサポーターで、筋肉量低下の手助けをし、終わった時には、アイシングや湿布でコンディションの改善をします。 又、激しく練習した時には、銭湯で水風呂、温かい湯に浸かるなどを数回繰り返したりして、翌日?に来るであろう筋肉痛に備えたりします。 卓球大会参加後にはマーサージなどで体全体の筋肉を整えて、永く卓球が出来るよう心掛けてはいます。 ですが、毎年毎年、歳を重ねるのは努力外のことで仕方ありません。^^; 卓球の戦型を考えたり、道具を変えたり、まだまだ挑戦しているところです。 …では、湿布の本当の正しい使用方法はどれなのか、色々調べてみました。 ・ 医療機関や薬局で購入する冷感シップ薬は、水分気化により温度を下げる作用と鎮痛・消炎剤による血管収縮などの抗炎症作用があります。 最近では、薬効を排除して水分気化により温度を下げる効果だけを持たせた冷却剤(ひえピタクールなど)も市販されています。 どちらを使用するにしても、スポーツ現場で冷却効果を期待して使用するのであれば、水分気化よりも冷却効果の高い氷・冷水・アイス・パックを利用する方が有効でしょう。 家庭で足や手をちょっとぶつけたときなどは、さしみなどを買った際に付いてくる保冷材などを凍らせておけば、アイシングが出来ますね! 温湿布と冷湿布の大きな違いは成分の違いです。 温感シップ薬には、血管を拡張させる薬剤(トウガラシエキスetc.)が含まれています。冷湿布にはメントールという清涼感を与える成分が配合されています。 ・湿布の選び方 捻挫・打撲した時(急性症状)では冷湿布 肩こり・腰痛がひどい時(慢性症状)は温湿布 貼るタイミングとしては、血行が良くなったところに筋肉をより和らげるような発想で、お風呂上がりに貼るのがおすすめです。 ・けがの経験者や障害を持っている人の場合 健康な人に比べ、筋肉の機能・柔軟性や関節の支持性・可動性の低下が考えられます。 痛みや腫れがなくても自分の現状を十分把握して必要な局所に限定した念入りなアイシングや正しく湿布を貼りましょう。 ・運動で痛みや腫れが出るようなら、 第一にテーピング・サポーターによる保護、 第二に技術的な内容の見直し(無理のない正しい技術の取得)、 第三に筋力・可動・柔軟などのコンディション改善などの検討が重要です。 ①現在可能な練習内容を選別し~完治するまでただ安静にしているのでは、健康な部分の機能まで衰退させるだけで、スポーツ現場への復帰は遅れるだけです。 患部に影響しない練習を工夫しながら積極的にリハビリを行いましょう。 以下は、患部に影響が及ぶ可能性のある練習を行う時に行います。 ②無感覚になるまでアイシングする 通常は10~20分程度。 ③冷却後直ちに練習を開始する 冷却効果は長時間持続しないので速やかにしかも痛みのない範囲で慎重に行う。 ④再びアイシング 効果が薄れてきたら再びアイシングをしてください。2回目以降は短いアイシングで効果が現れます。 ⑤再び練習を開始する 状態を見ながら2~3回を目安に④・⑤を繰り返す。 ⑥最後にアイシングを行い終了する。 アイシングの方法 1.冷たい⇒痛い(「ジーン」とする感覚) 2.暖かい(感覚的に熱く感じることもある) 3.チクチクする(針で突かれるような感覚) 4.触った感覚がなくなる(皮膚感覚の麻痺や麻酔をした感覚) 参考まで… 「五十肩」… 『痛い』→『動かせない』『動かさない』→『硬くなる(拘縮)』→『動かすと痛い』という悪循環で肩関節拘縮(凍結肩ともいいます) 『硬くなる前に痛みをとり動かせるようにすること』が大切です。 「テニス肘」とか「肘の腱鞘炎」…1.上腕骨外上顆炎、2.上腕骨内上顆炎が正しい名称です。 テニスをやりたいなら、フォアとバックハンドのボールリフティングをお勧めします。 ボールを打つときに100%の力が必要だとすると、安静だけですと筋力は80%位に低下して、そのままですと復帰できません。 なんとか除痛をして、手入れをしながら100%以上の筋力を作っておく必要があるからです。 他にも膝痛や腰痛など卓球競技を続けていると、様々な障害が出てきます。 上記のアイシングや湿布を参考にしてみてはいかがでしょうか! まず、原因をハッキリ把握して、なが~く楽しく卓球が出来るよう自分を大切にしてあげましょう(^_-)-☆ |
|