
 |
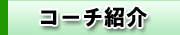 |
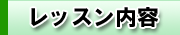 |
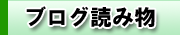 |
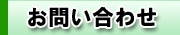 |
|
2013年02月23日更新
卓球競技の審判員
 先日の「全日本卓球選手権大会」などで、試合競技に欠かせない審判員の人達の活躍も見えましたね。 どの競技でも審判員がいなくては成立しません!! 東京の地で行われた「全日本選手権大会」では赤いブレーザーにベージュのスラックスと言う服装で 競技サポートをしていました。 神奈川では、紺ブレザーとグレーのスラックスという服装で審判を行います。 6月12日~16日、等々力アリーナで開催される「日本リーグ」の5日間、全日の審判協力を依頼されました。 小さな大会での審判は経験していますが~もう一度、しっかり「審判員の手引き」を勉強したいと思います。 「審判員」の手引きから~ ●競技領域への「入場」に関する手順 1、主審、副審は1列に並び、主審が先導して所定の競技領域に向かう。 2、主審、副審は一つのチームとして、落ち着いた歩調で真っ直ぐ歩く。 主審…対戦カード、ボールの箱を左手に持ち先頭に立つ。 競技者が一緒に行進の場合は、主審、上位シート選手、下位シート選手、 その後に副審の順に行進する。 3、主審、副審はバック等手荷物を持って競技領域にいかない。 業務に必要な「筆記用具」「ストップウォッチ」「ネットゲージ」「黄、赤、白カード」 はポケットに入れる。 プレーイングサーフェス用雑巾、チーム名表示板(団体戦)、得点表示板なども確認しておく。 4、審判員は、フェンスを跨いで乗り越えてはいけない。 主審はフェンス移動(通る空間を作る)、通り過ぎたら副審が元通りにする。 5、競技領域に入る場所は、主審席に近い角から入る。 6、競技領域に入ったら、主審と副審共に真っ直ぐに主審席に向かう。 7、主審席に到着したら、主審は対戦カードを椅子に置き、主審席を挟んで右側に主審、 左側に副審がテーブルに向かって立ち「一礼」してから業務につく。 ・選手紹介がある時⇒主審の右側に上位シード競技選手(組)、副審の左側に 下位シード競技選手(組)が並ぶ。 ・団体戦の場合⇒⇒⇒テーブルを挟んでチームが整列するので、 オーダーの発表方法など主審が行う場合は、方法も審判長の支持に従う。 8、審判員紹介のアナウンスがある場合は、名前を呼ばれたら、一歩前へ進み出て 「一礼」し、また戻る。 (注)振り向いたり、手を振ったり、お辞儀はしない。 その後、主審の支持で、主、副審同時にマッチ前の業務を開始する。 ◆主審の業務(ゲーム開始宣告の前迄の…) ①競技者の確認⇒対戦カードの氏名、所属、ゼッケンを確認する。 ②服装の点検⇒⇒(ベンチ到着時)服装の「JTTA」マークの確認する。 対戦者(チーム)同士の服装が共に似通っている場合は、どちらかに交換を伝え、 双方とも交換に同意できない時はジャンケンで敗者に交換を伝える。 ③用具の点検(ラケット)⇒日本製の場合:「JTTAA」のマークとメーカーの「ロゴ」を確認する。 外国製の場合:審判長の許可を求める。 ラケット本体が、連続した均一の厚さであるかを確認。 ラケット本体の主たる部分は気であるかを確認する。 (ラバー)⇒平坦性について確認する。 JTTAかITTFのロゴの確認をする。 ラケット両面の色について確認する。 (ペンフォルダーも裏面を点検する) ラケット本体に対してのはみ出し、欠損が2mm程度か確認。 (接着剤を含め厚さのチェックをする) ※競技者の確認、服装の点検、ラケットの点検は競技者全て揃う前でも可能であり、 競技者のベンチサイドでも良い。 (ラケットを預かり、テーブルに置く) ④アドバイザーの確認⇒個人戦の場合は、アドバイザーを確認する。 ⑤ジャンケンの実施⇒⇒サービス、レシーブ、エンドの選択。 ⑥対戦カードの記入⇒対戦カードに「S」、「R」と記入する。 ⑦規定の練習⇒⇒⇒予め選んでおいた使用球の中から1個を選び競技者に渡す。 (他のボールはポケットに入れておき、ボールが破損した場合に使用する) ⑧練習の終了時⇒⇒タイムキーパーの「タイム」の宣告を確認し、右手を高く上げ「ストップ」と宣告する。 ◇…………………………………………………………………………………………………………………………◇ ゲーム開始宣告⇒「○○・ヴァーサス・○○・ベストオヴファイヴ(セヴン)・ ファーストゲイム・○○トゥ・サーヴ」「ラヴオール」 1ファースト、2セカンド、3サード、4フォース、5フィフス、6シィックス、7ファイナル(セヴンス) マッチ終了時の宣告⇒「ゲイム・アンド・マッチ・トゥ○○」と宣告する。 ◇…………………………………………………………………………………………………………………………◇ ●競技領域からの「退場」に関する手順 1、主審、副審及びストロークカウンター其々は、全ての業務が終わったら、 主審席をはさみ、競技開始前と同様の場所で、ストロークカウンターは、 副審の左に位置し、起立し「一礼」する。…その後退場する。 2、競技領域からの退場…主審、副審、ストロークカウンターの順に並び、 入場と同じ経路で揃って退場する。 3、主審は対戦カードに審判長のサインを求める。 ※バット・マナー、違反のアドバイス等があった場合には、その内容について対戦カードの 欄外に記載し、口頭で報告をする。 4、主審は、対戦カードを所定の担当に渡す。 大分、勉強になりました。 大きな大会観戦で、卓球競技以外、審判部の皆さんの業務にも気になり、時々目がいっていました。 自分が参戦するローカル大会でも正式に声を出して審判をするよう心がけています(ohtuka) 「私がこの資格取得後、何度かルール改正された、ルールブックと審判手引きが配布されています。 この中には、分かったものではカットマンとの促進ルールの点数も改正されているそうです。 今、これを手配したばかりです…24年度版の手引きで、改正されたルールは次回お知らせします。」 |
|