
 |
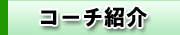 |
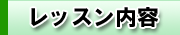 |
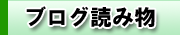 |
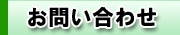 |
|
2012年05月25日更新
“伸びて 止まって”
 30年近く「裏ペンホルダー」の戦型を、2年前から「表ラバー」に戦型を変えた。 「表ラバー」について何もわからず、考えず、考えられず、 参加したシングルスの試合で偶然にも優勝した経験が一度だけある。 私は「表ラバー」に向いていたのだと、気を良くして練習を重ねているうちに、 段々、試合成績に結びつかない時期がきました。 「表ラバー」が分かってきて、ステップアップの時期に差し掛かったのでしょう。 それでも試合に参加し続けると、私の以前を知っている人達から 「なぜ、戦型を変えたの?」と言われることが多々ありました。 試合の成績は当然良くないことは分かっていました。 “弱くなったから元に戻そう”と考えがちだが、ポジティブに考えたのと 「表ラバー」の良さと悪さも実感出来るように成った事が、 そのまま続けている理由だと思います。 ある本では……新しい事に挑戦すれば、一時的に成績は落ち込むものだと 最初から分かっている人ならば、ステップアップできるまで辛抱強く待てます。 しかし、直ぐに結果だけを求める人だと、新しい技術の習得を諦めて、 また元の状態に戻してしまうのだと書かれていました。 「伸びて 止まって」を繰り返す選手…伸びない時期も必要だそうです。 伸びない期間をなるべく短くすることも大切、成長が停滞時には、 その理由を探ることも肝心だということです。 習得の学習曲線は大きく4つに分けられる。 ①S字を描く様に前半と後半に伸びて、中間がフラットなタイプ ②緩やかに成長し続けるタイプ ③中々伸びが見られず最後にグッと伸びるタイプ ④最初に急激に伸びてあとは緩やかに成長していくタイプ 殆どの人は①のS字タイプだそうです。 私自身どのタイプだか分からず、ただひたすら練習を重ねてきました。 現在は、約1年前に「中国ペンホルダー」の裏面スマッシュが出来るように 戦型を変更し、ひたすら裏面バックハンドの練習をしています。 こんな練習の中でも、裏面で「バックカット」をやってみたり、 表ラバーで「フォアカット」はどうかな?と、幅が広がり、今では楽しみながら 練習しています。 こんな中、教室でコーチからは「ロビング」や「フォアカット」のボールを 送ってくれました。 表になってからロビング練習も遠のいていましたが、先日の試合では、 相手にスマッシュをされ、「ロビング」3回の末、相手のミスで 一点を取ることが出来ました。 教室の練習成果でしょうね! 又、「フォアカット」も相手の下回転が強く、表ラバーではドライブも しきれない場面が多々ありました。 このカット練習も、きっと試合で役立つ時があると思います。 教室でこの技術を、自分には必要、必要ではないと考える人達も いるのではと思いますが、今現在のランクでの勝利につながる技術だけを、 追い求める人が多いのではないでしょうか? 私の経験からも、カットをやって、カットマンの事を知ったり使ったり、 ストップやバックハンド… 卓球の技を体感することで、ボールに対して緩急のあるタッチが出来たり、 卓球の幅が広がるでしょう。 指導資格取得を切っ掛けに「シェークハンド裏裏」も練習してみました。 「バックハンド」「バックボレー」を遣っているうちに中ペンの 「裏面バックハンド」が出来るようになりました。 まだまだ、試合では20~30%くらいの割合でしか出来ませんが 「裏面バックハンド」が見事に決まった時の醍醐味は格別のものがあります。 教室での、卓球技の全ては、ボールの角度、足運び、体重移動など、 自分での体感と実際に遣っていることでは開きがあります。 常にやれない技術のため、コーチの言われた言葉すべてを受け入れ、集中します。 後で、コーチの言葉を思い出しながら、言われた理由や試合での使い道を考え、 ノートに書いておきます(O) 皆さんも、卓球の幅を広げる事が、目先の結果より、 遠回りでも上達の早道と思いませんか? いかがでしょう(^^) |
|